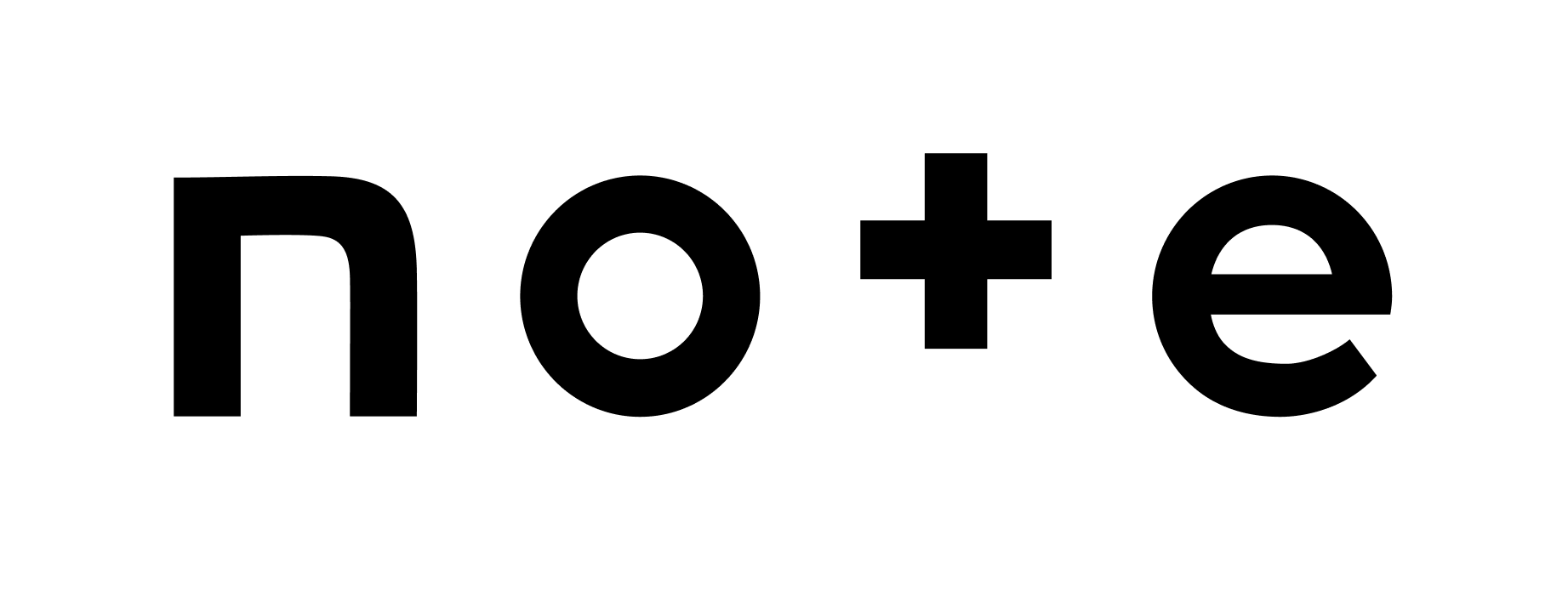色についての「いろは」
色についての基本を再解説します
印刷の世界では、デジタルディスプレイや日常の色と異なる考え方で色が扱われます。 例えば、RGB、CMYK、そしてLabカラーといった色の表現方法があり、用途や目的に応じて使い分けられます。 また、印刷では色の管理が非常に重要で、特にブランドカラーの再現や、画面と印刷物で同じ色を実現するための工夫が欠かせません。 ここでは、色に関する基礎知識や、印刷でよく使われる色の表現方法について解説します。
[色について]RGBとCMYK:デジタルと印刷の違い
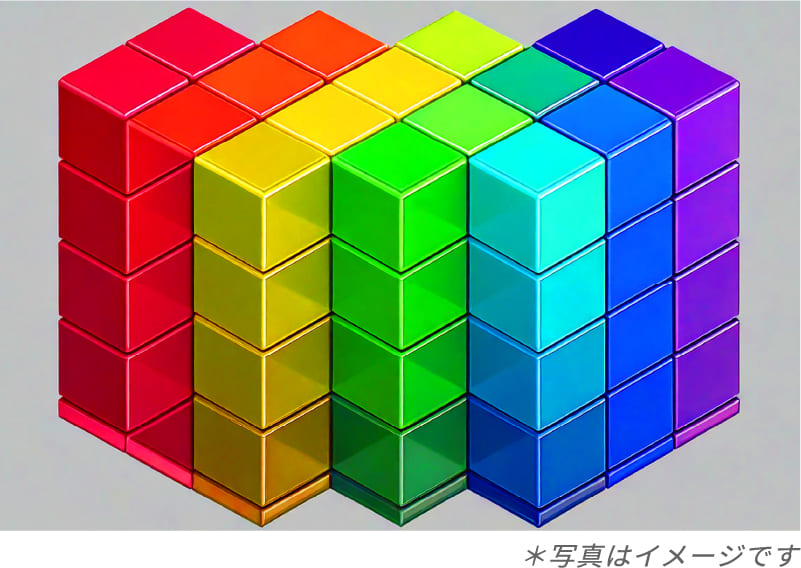

RGBとは?
RGBは「Red(赤)」「Green(緑)」「Blue(青)」の3色からなる色空間で、主にデジタルディスプレイでの色表現に使われます。
ディスプレイでは、この3色の光を重ね合わせる「加法混色」によって色を再現し、全てを重ねると「白」になります。
RGBは鮮やかな発色が可能で、ディスプレイ上では非常に魅力的な色表現ができますが、印刷には直接的に使用できません。
印刷物に近づけるためには、CMYKに変換して出力することが一般的とされます。
ポスターチャンネルや、RGB印刷を行なっているサイトは、印刷機のインクの色域のカバーによって、擬似的に印刷を行なっています。
CMYKとは?
CMYKは「Cyan(シアン)」「Magenta(マゼンタ)」「Yellow(イエロー)」「Key Plate(黒)」の4色を使用した色空間で、主に印刷に用いられます。
印刷物はインクを紙に重ねる「減法混色」によって色を表現するため、白い紙にインクを重ねていくと暗くなり、すべてのインクを混ぜると黒に近づきます。
元々はCMYの3色を均等に重ねると「黒」になる考えでしたが、実際は鈍い色となり、結果「黒」のインクが追加されました。
印刷物ではCMYKが基本の色設定です。
ポスターチャンネルへの入稿は、Adobe IllustratorなどのCMYK設定が可能であればその設定で入稿ください。
元がRGB形式の画像でCMYKに変換した際、大幅に彩度が落ちる場合はRGBのままご入稿ください。
[色について]Labカラー:色の精密な管理に使われる色空間

Labカラーは、Photoshopなどのデザインソフトでサポートされる色空間の一つで、人間の視覚に基づいて色を定義する方式です。
Labカラーの「L」は輝度、「a」は赤から緑、「b」は青から黄色までの範囲を示す軸で、3つの要素によって色を表現します。
LabカラーはRGBやCMYKよりも広い色域を持ち、人間の目に見える色をより正確に表現することが可能です。
そのまま印刷に使用することはまずありませんが、精密な色調整や色補正を行う際に役立つ色空間で、デザインの工程においてLabカラーが役立つ場面もあります。
[色について]DICカラー:日本独自の色指定システム

DICカラーは、日本で広く使われている色指定システムで、DICグラフィックスが提供する色見本です。
日本の印刷業界で信頼されている標準色として、多くの企業やブランドで使用されています。
DICカラーを使用することで、デザイン時の色が印刷物でも正確に再現されるよう管理できます。
CMYKの苦手とするオレンジ色など掛け合わせの色をDICカラーで代用したり、企業の商品パッケージをより鮮やかに正確にする際に使用します。
DICカラーはオフセット印刷のため、ポスターチャンネルでは取扱は行なっていません。
1色のDICカラーで1版となるため、印刷物にDICカラーを追加すると、CMYK+1色の扱いで5版となり、その分、印刷コストも上がります。
[色について]PANTONEカラー:グローバルで使われる標準色

PANTONE(パントーン)は、世界的に利用されている色指定システムです。
多くのデザインや印刷の現場で標準的に使われており、特に企業のブランドカラーやロゴの色管理に欠かせない存在です。
PANTONEは世界基準のため、国外に印刷物を特色で入稿する際、そのまま通用します。
ちなみに、ポスターチャンネルのインクジェットプリンターには、PANTONEの近似色を再現できるプラグインが搭載されています。
このため、PANTONEの指定色に対して機械の色域範囲内での再現が可能です。
ただし、すべてのPANTONEカラーを完全に再現できるわけではなく、近似色としての出力となるため、微妙な色の違いが生じる場合があります。
[色について]マンセル値:曖昧な色を数値化
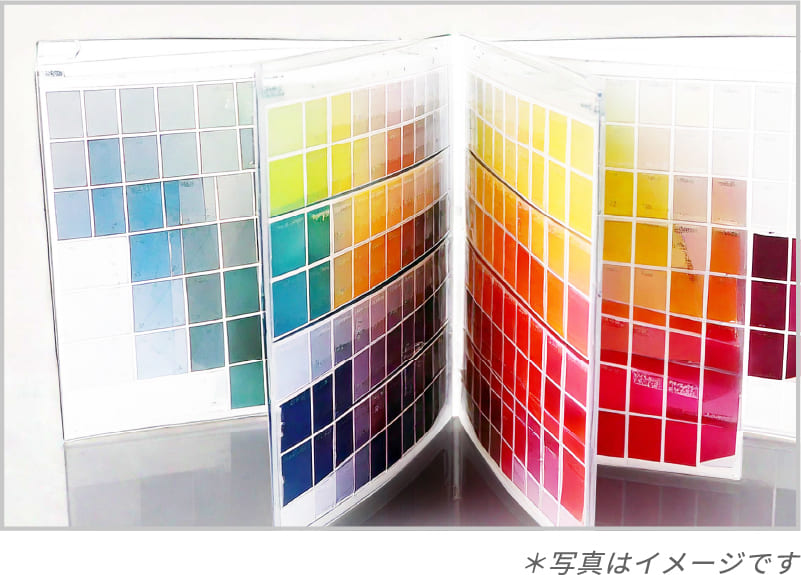
マンセル値は、色を数値で表現する体系で、曖昧に呼ばれていた色を数値化したものがマンセル値です。
アメリカの画家・美術教育者のアルバート・マンセルによってつくられました。
ひとつの色を「色相」、「明度」、「彩度」の3つの属性で表すものです。
日本では主に製品の色管理やデザイン、そして都市の景観形成に活用されています。
製品の色管理では、塗料や建材などの色を正確に再現するために、マンセル値が標準的な指標として用いられます。
これにより、異なる製造ロット間や異なる製造拠点間での色のバラつきを抑え、品質の安定化に貢献しています。
デザインの分野では、建築物やインテリア、製品のデザインにおいて、マンセル値を用いて色の組み合わせや調和を数値的に分析し、視覚的に心地よい空間や製品をデザインすることができます。
また、照明設計においても、光の色温度をマンセル値で表現することで、空間全体の雰囲気をコントロールするのに役立てられています。
マンセル値の解説において、ポスターチャンネルとの関係性無いようですが、実は1つだけあります。
それは、屋外広告物条例です。
東京都をはじめ、景観や風致の向上、公衆の危害を及ぼす恐れのない広告物かの判断に用いているのがマンセル値です。
特に大きな看板の場合、市区町村に広告物の色をマンセル値で提出する場合もあります。
このように、マンセル値は、日本の様々な分野において、色のコミュニケーションを円滑にし、製品や空間の品質向上、そして都市の景観形成に貢献していると言えるでしょう。
[色について]その他、国際的な標準カラーを紹介
日本ではあまり馴染みがありませんが、国際的な基準カラーをご紹介します。
1. NCSカラー(Natural Color System)
スウェーデンで開発されたカラーシステムで、自然の見え方に基づいて色を定義しています。
視覚的な色の知覚に基づき、色を識別しやすくするためのシステムで、インテリア、建築、製品デザインなどの分野で使用されることが多いです。
NCSカラーは、色の構造や表示に優れ、国際的にも広く使われています。
2. RALカラー
ドイツで広く使われる標準カラーシステムで、塗料やコーティングなどにおける標準色として多くの分野で利用されています。
RALカラーは、建築や製品デザイン、工業分野における塗装や装飾の標準色として、ヨーロッパを中心に非常に広く普及しており、色番号によって色を管理しています。
3. ANSIカラー
ANSI(アメリカ国家規格協会)が定めた色規格で、主に配線や安全標識、産業用設備の配色など、特定の業界基準に従った色分けに利用されています。
産業や工業における安全色や配線色としてアメリカで多く用いられています。
4. Fed-Std-595カラー
アメリカの軍事および政府機関向けの標準色です。
軍用車両、装備、機器などの色分けで広く採用されており、特定の耐久性や環境条件を満たすことが求められる場面で使用されています。
5. ISOカラー
ISO(国際標準化機構)が制定した標準色で、特定の業界向けの安全標識や製品デザインに用いられることがあります。
色の名称や数値で定義され、産業の安全管理や品質管理などに役立っています。
[色について]まとめ
基本的なカラーを解説しましたが、ポスターチャンネルに直接関係するカラーは、CMYKとRGBになります。
さらには印刷物用としてはCMYKが本来の基準となります。RGBは光の三原色ため、「RGB印刷」と表示している時点で矛盾がありますが。近似色でカバーしています。
そして、ポスターチャンネルの10色インクは、CMYKのデータを元に、表現しにくい色域をカバーするためのインクが追加されています。
ですので、オフセット印刷に比べ発色や色の表現力が優れています。今では、家庭用のプリンターでも4色以上の多色インクが主流ですね。