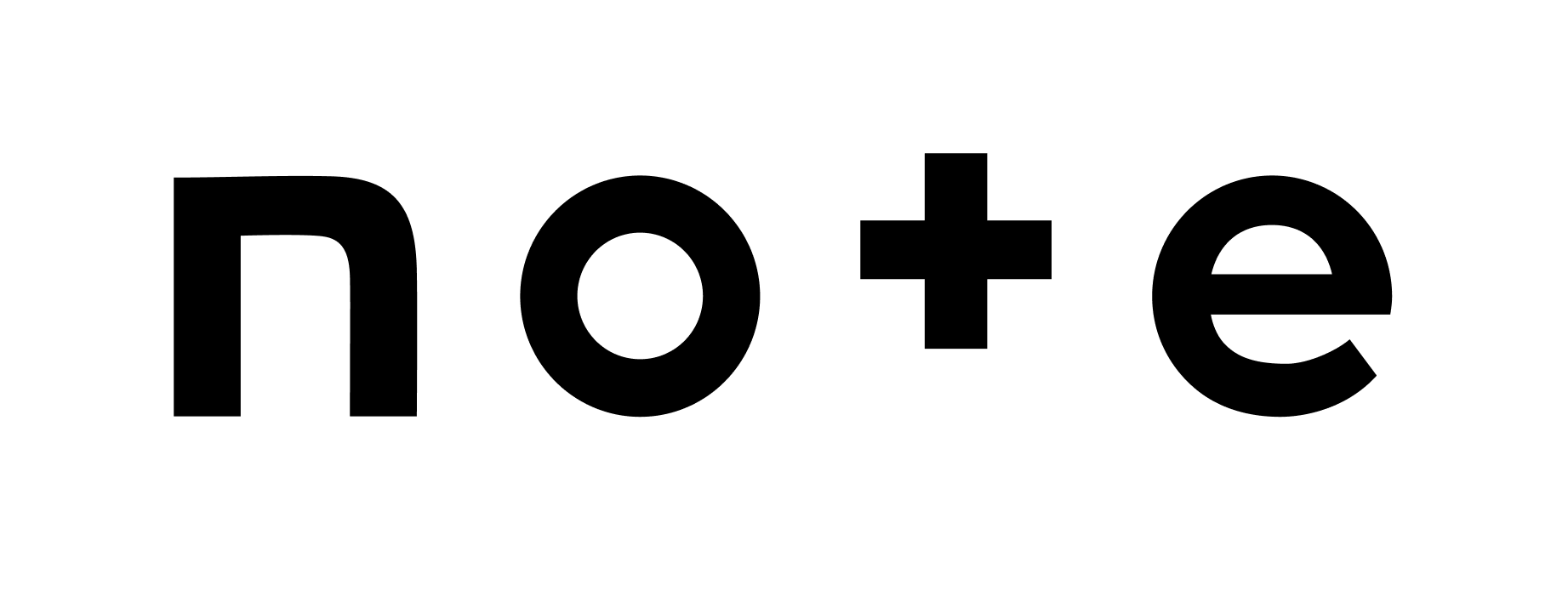正月の縁起色について
正月を彩る色を解説
もう間もなく新しい年となりますね。 お正月には、縁起の良い色が生活や行事にふんだんに取り入れられています。 これらの色は、単なる装飾ではなく、古くからの風習や文化に基づいた特別な意味を持っています。 本記事では、正月にまつわる縁起色やその背景についてご紹介します。
[日本の縁起色]紅白:新年を祝う基本の色

紅白は、日本の祝い事で欠かせない色の組み合わせです。
どなたでもご存知ですね。
正月には紅白の餅や幕、飾りなどでその組み合わせが多く見られます。
紅(深い赤)は「喜び」や「活力」を象徴し、白は「純粋さ」や「新しい始まり」を表します。
この2色が調和することで、生命の躍動感と清らかさを表現しているとの事です。
赤と紅の違い
興味深いことに、日本では「赤」ではなく「紅」という表現が用いられることが多いです。
その背景には歴史的な理由があります。
古代中国では、「赤」という色が貧困や裸(衣服を持たないこと)を意味する負のイメージと結びついていました。
このため、日本では「紅」という高貴で洗練された色が祝い事に用いられるようになりました。
紅は平安時代には紅花から抽出された染料として、貴族の女性の衣装や化粧品に使われたとか。
そのため特別な価値を持ちました。
その結果、「紅」という色が高尚で縁起の良い色として定着したとされています。
正月の紅白餅や紅白幕は、この紅白の組み合わせを通じて、新年の清々しさと喜びを表現しています。
[日本の縁起色]金と銀:豪華さと調和を象徴
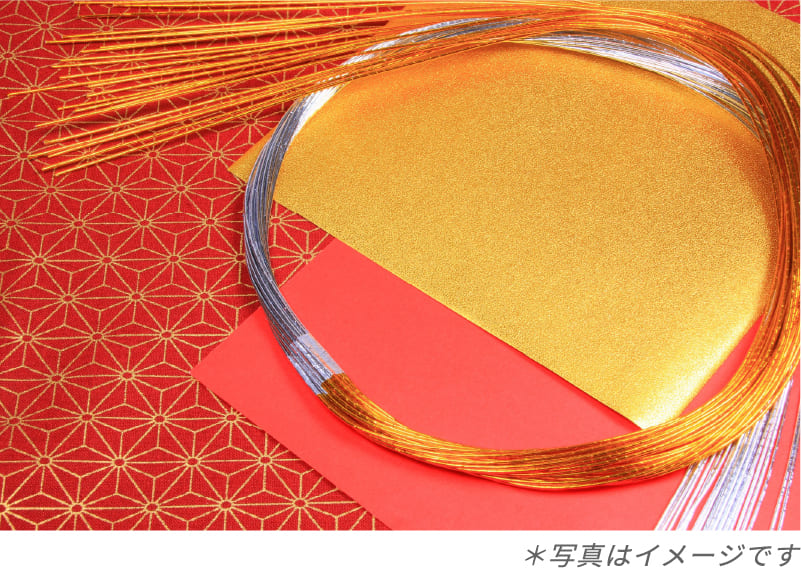
金と銀は、正月飾りの中で特に目を引く色です。
金は富や繁栄を表し、銀は静かで調和のとれた美しさを象徴しているとされます。
これらの色は、華やかさと落ち着きの両方を兼ね備え、新年の始まりにふさわしい意味を持っていますね。
門松やしめ飾りへの応用
門松やしめ飾りに使われる飾り紐や金銀箔の装飾は、正月らしい豪華さを演出します。
また、これらの色は神聖な場や儀式に用いられることが多く、神様を迎えるための準備としての意味も込められています。
金銀の組み合わせは、正月だけでなく結婚式などの祝い事でも使われ、日本人にとって特別な意味を持つ色彩です(ただ派手に飾っているだけではないのですね)。
[日本の縁起色]緑と橙:自然と家系の繁栄

正月飾りの中で目立つのが緑と橙の組み合わせです。
緑は松や竹の色で、不老長寿や力強い生命力を象徴します。
一方、橙(だいだい)は「代々」という言葉に通じ、家系の繁栄や子孫の繁栄を願う意味が込められています。
松と橙の由来
松は常緑樹であり、一年を通じて緑の葉を保つことから、不老長寿の象徴とされています。
一方で橙は、その実が木に長期間留まることから、家族や家系が代々続くことを願う象徴となっています。
このため、鏡餅の上には必ず橙が乗せられる習慣があります。
緑と橙の組み合わせは、自然の恵みと家族のつながりを表現するものとして、正月飾りに欠かせない存在です。
[日本の縁起色]黒:正月の袴に込められた意味

黒は通常、厳粛さや格式を象徴する色として、日本文化において広く使われています。
特に正月に男性が着用する袴は、黒を基調としたものが伝統的です。
黒の袴は「礼節」と「謹厳」を表し、新年という特別な時期にふさわしい装いとして選ばれてきました。
正月の黒袴の由来
黒袴は武家社会での正式な礼装として定着しており、現代では結婚式や成人式といったハレの日にも着用されます。
正月における黒袴は、新しい年を迎えるにあたり、身を引き締めて神聖な場に臨むという気持ちを表しています。
黒という色が持つ「締まり」や「威厳」のイメージが、新年の祝いの場に重みを与えます。
他の黒の使い方
正月料理の「黒豆」にも、黒が使われています。
「黒」は健康を守る力があると信じられ、「黒豆を食べると元気でいられる」とされる縁起担ぎの意味が込められています。
また、正月飾りでは、黒が全体の色彩を引き締める役割を果たすこともあり、金や赤などの明るい色を際立たせる効果を持っています。
黒は派手さこそありませんが、日本の伝統文化において重要な役割を果たしており、正月のシーンにも深く根付いています(おせちの重箱など)。
[日本の縁起色]朱:日本文化と正月における神聖な色

朱は、日本文化において古くから特別な意味を持つ色です。
その鮮やかな赤みを帯びた色彩は、太陽や火を象徴し、生命力や神聖さを表現する色として用いられてきました。
特に神社の鳥居や仏具、儀式用の道具など、重要な場面や物に朱が使われるのは、この色が持つ浄化の力を信じているからです。
正月と朱の関係
正月に朱色はさまざまな形で登場します。
例えば、門松やしめ縄に飾られる和紙の飾りに朱が使われることが多いですね。
朱は魔除けの意味を持つため、新年を迎える家の出入り口に飾る正月飾りに用いることで、外部からの邪気を払い、家を清める役割を果たしています。
また、正月の祝い酒に使われる漆塗りの杯(盃)やお重の装飾などにも朱が用いられ、その鮮やかな色が祝いの場を引き立てます。
朱の文化的背景
朱色は、奈良時代から平安時代にかけて日本に伝わった「丹(に)」という顔料をもとにした色です。
朱には防腐効果もあることから、古墳や仏像の彩色に用いられ、さらに身を守る色として広まっていきました。
その後、神社の建築物や神具に使われるようになり、神聖なイメージを持つ色として定着しました。
[日本の縁起色]朱と紅の違い:明確な使い分け

一見似ている朱と紅ですが、日本ではそれぞれに異なる役割や用途が与えられています。
この違いは、色の発色や文化的背景によるものです。
朱:神聖で力強い色
朱はややオレンジがかった赤で、太陽や火といった自然のエネルギーを象徴します。
そのため、主に宗教的な儀式や建築物に使われる色です。
前述したように、神社の鳥居や祭壇、そして正月の飾りに朱が使われるのは、神聖さや魔除けの力を持つ色としての役割を果たしているからです。
紅:華やかで祝福の色
一方、紅は純粋な赤色で、華やかさと美しさを象徴します。
紅は女性の装いや化粧、または祝い事で使われる色として馴染みがあります。
例えば、振袖や婚礼衣装に用いられる紅は、祝福や繁栄を意味します。
また、紅白饅頭の「紅」は、白と共に吉兆を示す組み合わせとして用いられています。
使い分けの具体例
朱:鳥居、漆器、正月飾り
紅:振袖、紅白幕、紅白饅頭
このように、朱は神聖で力強い「守り」の色、紅は華やかで「祝い」を表す色として、それぞれの場面で使い分けられています。
[日本の縁起色]そんな縁起色を印刷しませんか?
正月を彩る縁起色には、それぞれの色や組み合わせに深い意味と由来があります。紅白や金銀、緑橙といった色彩が、新しい年を迎える心を豊かにし、希望を象徴しています。今回ご紹介した色の背景を知ることで、正月の飾り付けがより意義深いものになるでしょう。
ポスターチャンネルでここまでご紹介したカラーを印刷してみませんか?
当サイトの高い再現性のインクジェットプリンターで印刷が可能です(金色・銀色は対象外)。
ご注文お待ちしています。